ご覧いただいている皆さまへ!
夏休みの「自由研究や科学工作」にお困りではありませんか?
ネット上には「アイデアやテーマの選び方」についての情報がたくさんありますが、自由研究の本当の目的を考えたことはありますか?
自由研究の意義を理解し、お子さまの成長につなげましょう!
- 自由研究はなぜあるの?
- 自由研究・科学工作での教育のねらいは?
- 親のサポートはどこまで?
- 低学年は、科学工作がおすすめ
- 男女別!おすすめ小学校低学年!科学工作キット【8選】
「自由研究」はなぜあるの?
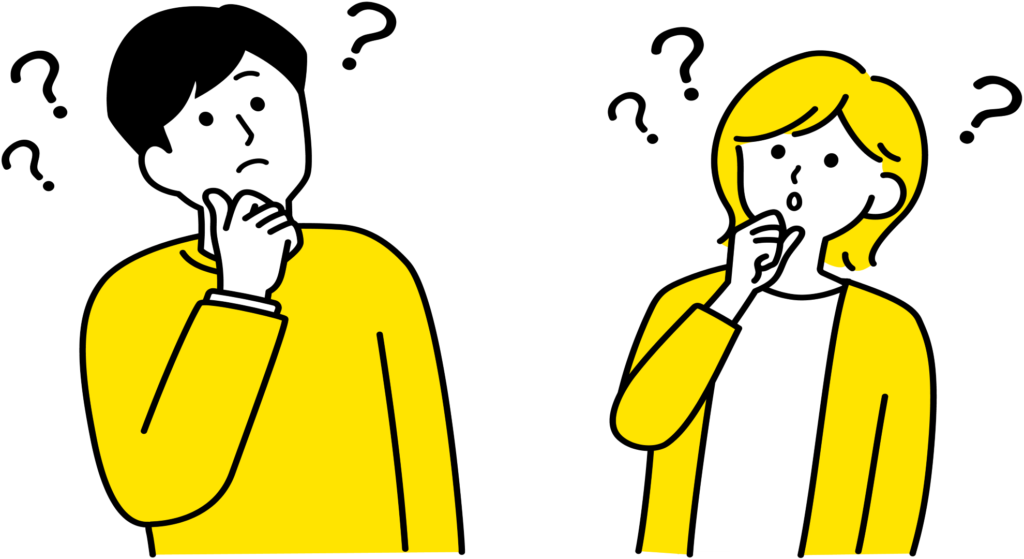
自由研究は、興味や関心に基づき自由にテーマを選び、調べ学ぶことです。
これにより、子供たちは自主性や探究心を育み、問題解決能力や創造性を養います。
自由研究は、子供たちの成長と学習意欲を促進する役割を果たします。
一緒に子供たちの成長を応援しましょう!
「自由研究」の始まりは1947年(昭和22年)
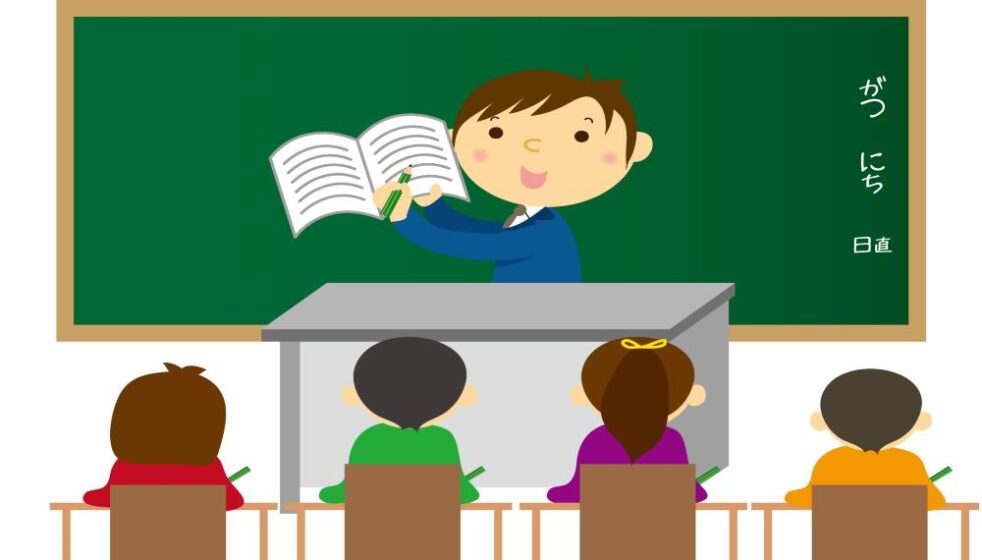
1947年、戦後の教育改革で「自由研究」が導入されました。
これは子どもたちの自主性を促進するためでしたが、教育の歴史が浅く、1951年には廃止されました。
総合的な学習時間
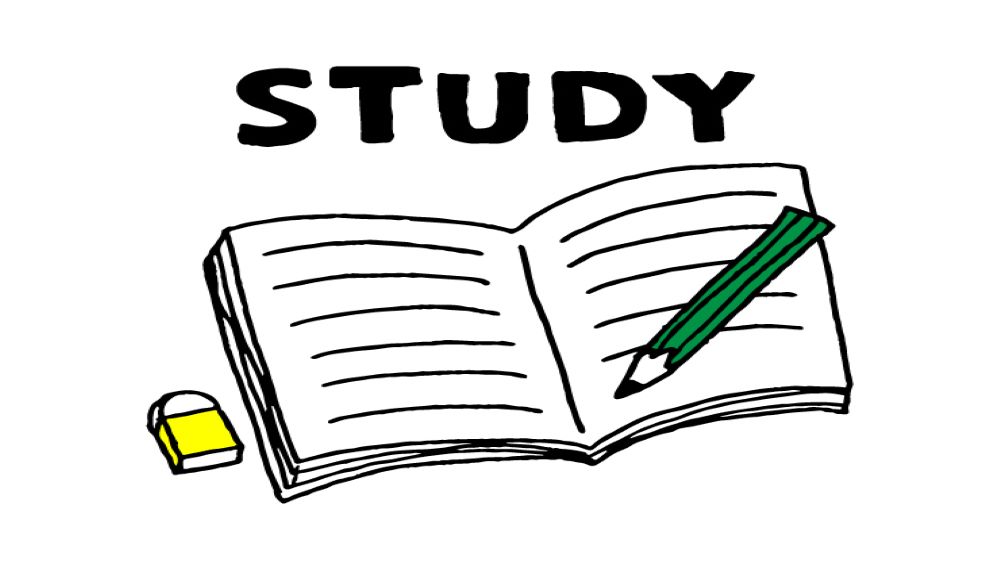
2000年度に始まった「総合的な学習の時間」は、子どもたちが自ら問題を見つけ、学び、考え、主体的に判断する時間です。
この時間は、地域や環境などの身近な問題を取り上げ、子どもたちが自分で行動することで、「個の力」を強化し、将来の社会で必要な能力を身につけることを目的としています。
このプログラムを通じて、子どもたちはより実践的なスキルを習得し、自主性と創造力を高めることができます。
将来の社会において重要な役割を果たすための基礎を築く大切な時間です。
-300x300-1.jpg)
個の力はこれからの時代に求められる要素だね!
自由研究での教育のねらいは?
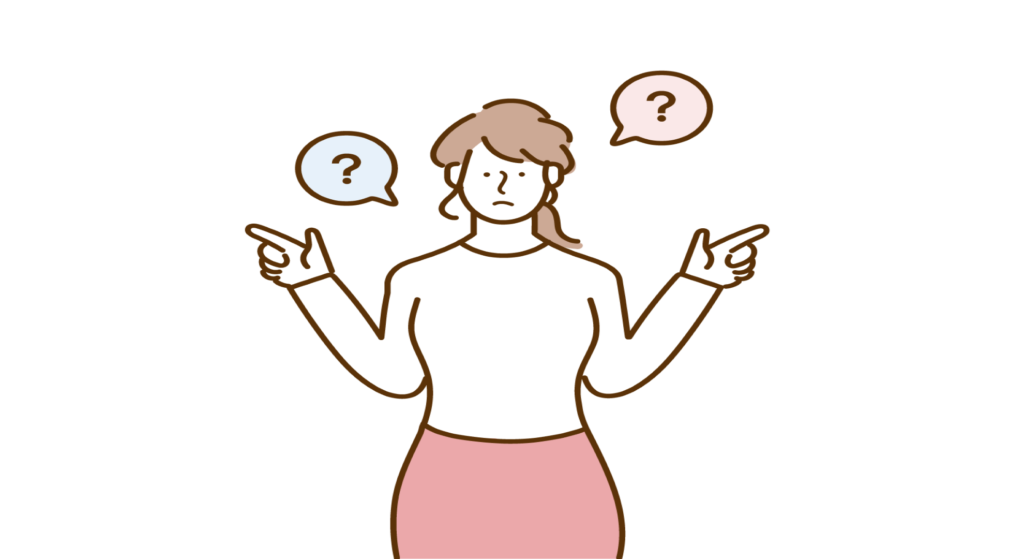
自由研究の目的は、問題解決能力、深い思考、創造性などの基礎を身につけることです。
具体的には、自分でテーマを選び、調査や実験を通じて課題を解決するプロセスを経験します。これにより、子どもたちは情報収集や分析、仮説の立て方、結果のまとめ方を学びます。また、自由研究は自ら考え行動する力を育むため、将来の学びにも大いに役立ちます。
自由研究を通じて、子どもたちは自主性や責任感も養い、自己表現力を高めることができます。
- 問題解決能力
- 深い思考
- 創造性
なぜ夏休みの宿題に?

学びには大きく分けて2種類あります。
- 教えてもらい習って覚える学び
- 自分で課題を決めて深く学ぶ研究的な学び
学校の授業では、時間的に「習って覚える学び」に集中しています。
そのため、夏休みなどの長期休暇を利用して、「研究的な学び」に取り組むことが宿題となります。
これにより、さらに深い学びを得ることができます。
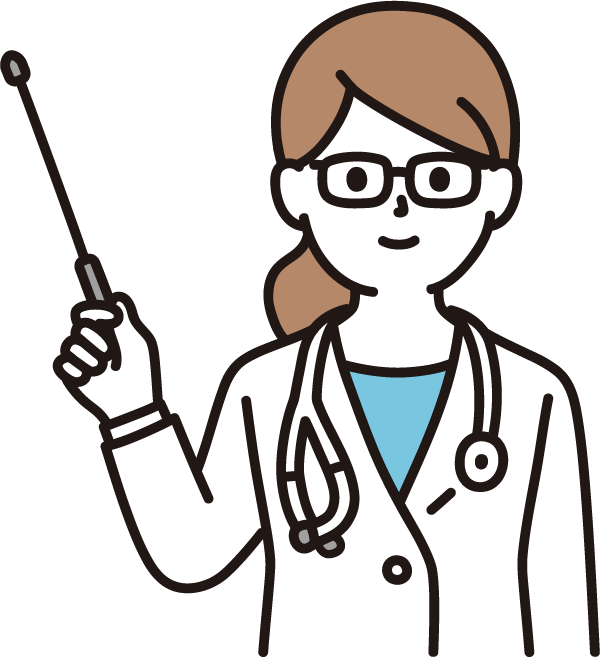
自ら学び、自ら考え、主体的に判断は、
大人になっても必要!
子どもの時から習慣化すると心強いね♪
長期的に研究を行い、学ぶ楽しさを!

夏休みは長期の休暇を活用し、子どもたちが自主的に研究活動を行う機会です。
これにより、学びの楽しさや面白さを体験し、自分でテーマを選び、計画し、実行するプロセスを通じて、問題解決能力や創造性を育むことができます。
これが「自由研究」の大きな目的の一つです。
自由研究に正解・不正解はない!

自由研究では、正解や完璧さよりも、自分が好きなことに没頭する経験が重要です。
自分の興味に熱中し、それをまとめることで自由研究が完成します。
「熱中できた」「楽しかった」といった体験は満足感を与え、自信につながります。
-300x300-1.jpg)
自由研究は、成長のチャンス!
親のサポートはどこまで?

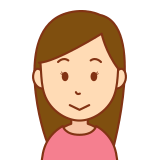
「親がどれくらい手伝っていいの?」
自由研究では、親が子供をどこまでサポートするかが重要です。
親は子供のやる気を引き出し、必要な資料や道具を提供し、アドバイスや指導を行います。
しかし、子供の自主性や成長を妨げる過度な介入は避けるべきです。
親は子供の成長を見守り、適切なバランスでサポートすることが大切です。
小学生にはサポートが必要?

研究を進めるための
基本的な組み立て方がわからない場合は、
以下のような方法でサポートすると良いです!
- お子さんがなぜその疑問を持ったのか、きっかけを一緒に考える。
- 疑問を解決するための方法や手順を一緒に考える。
- 結果や出てきた考えを共有し、それからどんなことを考えられるか一緒に考える。
研究の組み立ては難しいので、
ガイドラインを作成して答えの導き方を
イメージしながらサポートすることが
おすすめです。
お子さんが主体的に
取り組むことを大切にしながら、
一緒に進めていきましょう。
-300x300-1.jpg)
ちなみにこの組み立ては、
論文などと同じような組み立てので
難しいのは当たり前ですよね(汗)
低学年は、科学工作キットがおすすめ

低学年のお子さんに
科学工作キットをオススメする理由は、
以下のようなものです
- 子供たちの興味を引く
科学工作キットは、
色々なテーマや実験が含まれており、
子供たちの好奇心をくすぐることができます。 - 知識とスキルの獲得
科学工作キットを通じて、
子供たちは科学の基礎知識や
実験手法を学ぶことができます。
手を動かしながら学ぶことで、
理解が深まります。 - 創造力と問題解決能力の育成
科学工作は子供たちに
創造的な思考や問題解決能力を養います。
自分でアイディアを出したり、
試行錯誤しながら実験を
進めることで、
自信もつけることができます。 - 家族との共同作業
科学工作キットは家族と一緒に
取り組むこともできます。
親子のコミュニケーションや
協力の機会となり、
楽しい思い出を作ることができます。
これらの理由から、
低学年のお子さんには
科学工作キットがおすすめです!
キットを利用・活用しよう!

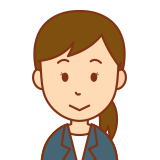
「低学年での自由研究は難しすぎる!」
と、感じている人には、
科学工作キットがおすすめです!
- 便利な情報やツール・キットを使ってもいい!
- お子さんにパソコンやタブレットを渡すだけじゃなく、親子で一緒に調べましょう。
- ツール・キットを上手に使いながら、お子さんならではのアイデアや工夫を考えて作品を完成させましょう!
親子で協力して、
楽しみながら自由研究を進めましょう!
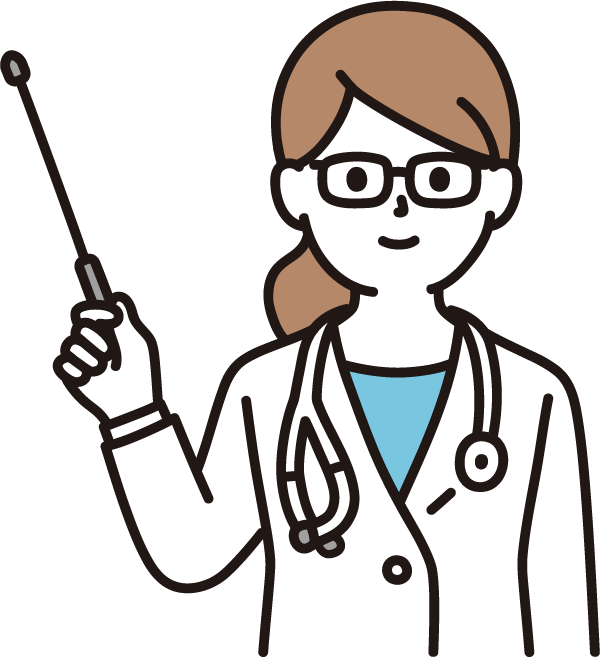
キットを使用したからと言って
内申点に大きな影響はありません。
男女別!おすすめ低学年!科学工作キット【8選】

小学校低学年!男の子におすすめ【4選】
小学校低学年!女の子におすすめ【4選】
まとめ

自由研究はなぜあるの?
戦後の教育改革の中で
1947(昭和22)年「自由研究」は、
教科の一つとして定めら子どもたちの
自発的な活動を促すことを目的としたが、
1951(昭和26)年に発展的に解消された。
自由研究での教育のねらいは?
問題を解決する力・物事の深め方や考える力、
独創性などの素地も身につけることが
自由研究のねらいです!
ガイドラインの作成
研究の組み立ての
基本を知らない・わからないので
主体的なことはお子さんが考え、
それ以外のところでサポートしてあげる
必要があります。


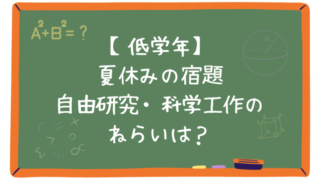
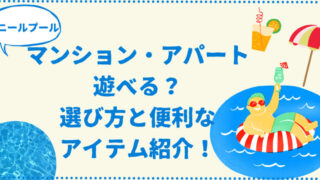
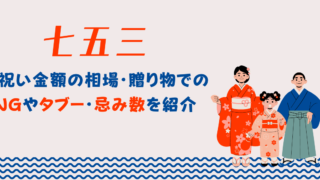

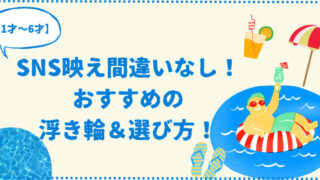
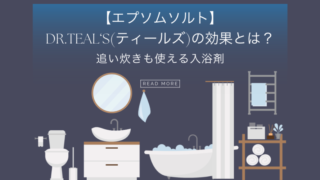

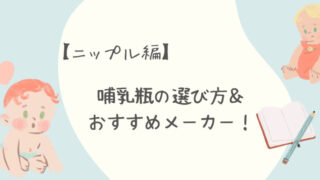

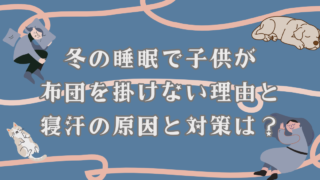
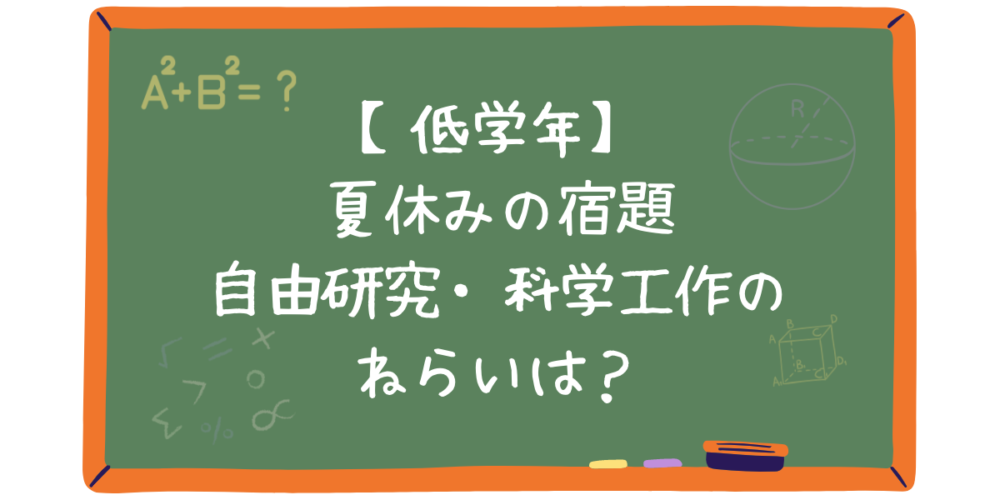










コメント